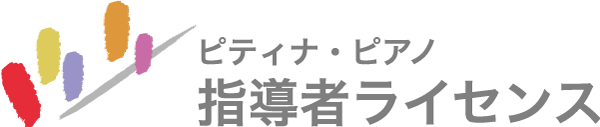
- トップ
- 概要
- 試験内容・学習ガイド
- エッセイ(小論文)
試験内容
エッセイ(小論文) ~セミナー受講を通して指導を学び、文章にまとめる
試験概要
各級の「課題レポート」およびピティナ・ピアノセミナーの「セミナーレポート」3点のコピーを提出し、指導者としての考え方や指導法を文章にまとめる能力を問う試験です。
課題レポートの内容
| 初級 | ピティナ・ピアノセミナー受講時の「受講レポート」(3講座分のコピー)、および、初級指導に関する1,200文字程度の課題レポート提出 |
| 中級 | ピティナ・ピアノセミナー受講時の「受講レポート」(3講座分のコピー)、および、中級指導に関する1,200文字程度の課題レポート提出 |
| 上級 | ピティナ・ピアノセミナー受講時の「受講レポート」(3講座分のコピー)、および、上級指導に関する1,200文字程度の課題レポート提出 |
セミナーレポートについて
ピティナWebサイト掲載のセミナーにご参加いただいた際に執筆いただいた「セミナーレポート」が該当となります。また、ピティナeラーニングの「レポート対象」動画を閲覧いただくことでも提出できます。
- エッセイ提出課題の「セミナーレポート」3点のうち必ず1点はレッスン見学レポートであることが条件になります。レポートは、セミナーオンラインレポート又はeラーニングレポートでご提出いただけます。
- セミナーレポート/eラーニングレポートについては、級区分はございません。
- 「紙のレポート」をご提出される場合は、スキャンデータもしくはPDFをアップロード下さい。ご自身での用意が難しい場合は充当することはいたしかねます。
- 必ずレポート内に、受検級・タイトル・氏名をお書きください。
審査書類の提出
- ▶提出フォーム:こちらより PDFまたはWord文書をアップロード
提出フォームよりご提出ください。※締切日必着
締切日は年3回(6月末、10月末、2月末)設けています。
セミナーレポートに充当するものにつきましては、セミナーの受講日時・セミナー名・講師名を合わせてお知らせください。
テーマ案
- 通常テーマ、指導案いずれかの1つを選び課題レポートを作成してください。
初級テーマ案
1.通常テーマ
1.初級指導の基本方針
-
ア.指導の言葉を選ぶポイント
-
イ.導入時期の子供にピアノの楽しさを教えるには?
-
ウ.導入期の5感の育て方
-
エ.導入期生徒の指導に際しての留意点
-
オ.導入期指導におけるピアノという楽器と子供とのかかわりにおいて、音楽全般を理解させる上において、留意するべき点
-
カ.私と音楽(ピアノ指導を通して何を子供に伝えたいか)
2.初級指導の教材
-
ア.導入における指導書の選び方
-
イ.導入期の教材選択のポイント?
-
ウ.初級教材への留意点5感の育て方
3.初級指導の基礎作り
-
ア.基礎教育の必要性
-
イ.土台作りの為の「これだけはおさえておきたい」ポイント
-
ウ.初級の基礎づくりとは
-
エ.初級のテクニック
-
オ.初級指導のソルフェージュ
-
カ.ソルフェージュの初級導入の必要性
-
キ.読譜導入の工夫
4.初級指導における生活と環境
-
ア.ピアノを通して努力する習慣の楽しさを身につける
-
イ.保護者とのコミュニケーションの大切さを学ぶ
2.生徒への指導案作成
-
ア.以下のモデルケースにおける、今後1年間の指導法・指導案を考え、具体的にまとめてください。
小学2年生男子。4歳からレッスンに通っており、先日バイエルが修了し、ブルグミュラーに取り組み始めたところ。
12 月に日本バッハコンクールに参加した。教室の発表会を6月に控えている。
他の習い事も多数しており、親も共働きのため、自宅での練習時間が限られており、基礎がまだしっかりしていないこと、また譜読みのスピードが遅いことが課題となっている。
-
イ.ご自身の生徒さんについて、抱えている課題とそれに対する指導法・指導案を考え、 具体的にまとめてください。
中級テーマ案
1.通常テーマ
1.中級指導の基本方針
-
ア.自立した練習で応用力を膨らますポイント
-
イ.学ぶ意識をさらに高めるための指導とは
-
ウ.中級で身につけるべき基本(ペダリング、打鍵、音色など)
-
エ.教師に頼らない、自立した解釈をさせる方法
-
オ.上級につなげる為の指導ポイント
-
カ.年齢とともに高度になる課題曲を演奏するに当たって、ぶつかってくる壁を乗り越えるための工夫
2.中級指導のレパートリー
-
ア.この時期に何をどう学ばせるか
3.中級指導のポイント
-
ア.中級テクニック
-
イ.表現力を伸ばす指導とは
-
ウ.曲の理解のさせ方
-
エ.バッハ インヴェンションについての指導法
-
オ.ソナチネアルバムについての指導法
-
カ.ピアノ演奏に最低限必要な技術力、分析力の基礎とは?
-
キ.楽譜から何を読み取るか?
-
ク.アナリーゼの必要性
-
ケ.ポリフォニックへの理解をより分かりやすく指導するための考察
4.中級指導における生活と環境
-
ア.ピアノを通して目標達成の方法を身につける
-
イ.学業との両立の方法
2.生徒への指導案作成
-
ア.以下のモデルケースにおける、今後1年間の指導法・指導案を考え、具体的にまとめてください。
小学5年生女子。ピアノを習って7年だが、3年前に転居に伴い、教室に移ってきた。バッハインヴェンションとソナチネアルバム1巻に取り組んでいる。2年前からピティナ・ピアノコンペティションに参加しているが、思うような結果が出ず本人・保護者ともにモチベーションが上がらずにいる。
-
イ.ご自身の生徒さんについて、抱えている課題とそれに対する指導法・指導案を考え、 具体的にまとめてください。
上級テーマ案
1.通常テーマ
1.上級指導の基本方針
2.上級指導のレパートリー
3.上級指導のポイント
4.上級指導における生活と環境
具体例:
-
ア.基本に則った奏法と、芸術性を高めること
-
イ.音楽を追求し続けていく姿勢について
-
ウ.和声的・対位法的アナリーゼに基づいた表現力と個性
-
エ.作曲家・歴史的背景の理解と演奏指導
-
オ.より幅広い表現の指導方法
-
カ.効率的な練習方法
2.生徒への指導案作成
-
ア.以下のモデルケースにおける、今後1年間の指導法・指導案を考え、具体的にまとめてください。
中学3年生女子。レッスンに通い始めて10年目。
毎年ピティナ・ピアノコンペティションに参加しており将来は音大への進学も視野に入れているが、高校は普通科に進学希望で、受験勉強との両立に悩んでいる。
-
イ.ご自身の生徒さんについて、抱えている課題とそれに対する指導法・指導案を考え、具体的にまとめてください。
エッセイ(小論文)科目の修了
各審査員の総合点により、事務局にて合否判定を行います。審査員3名の各採点の合計点が225点以上(平均点が75点以上)の場合が、「合格」となります。合否結果は締切日の約3~4週間後に郵送いたします。
<審査の観点>
3名の審査員により審査をしていただきます。レポートを作成する上で、下記のようなレポート作成の一般的な観点を参考にされるのも一つの方法となるでしょう。
① テーマ設定に関する項目
各課程に求められるピアノ指導のテーマとして、実践的で適切なテーマ設定がなされているか。
② 論理構成に関する項目
論理構成に関する項目
③ 考察力に関する項目
自分なりの視点をもって,課題を考察されているか。自分なりの考え方が述べられているか。
④ 文章表現に関する項目
誤字・脱字がないこと、文章の主語・述語の対応や引用の処理など、文章表現の基本ルールが守られているか。
⑤ 論述効果に関する項目
総合的な視点において、説得力のあるレポートになっていたか。レポートとしての論述効果はあったか。
<レポート作成の意義>
ピアノ指導者が、指導者としての考え方やご自身の指導法を説明する場面は、意外と多いものです。教室内の広報誌やホームページ、専門誌へのエッセイ投稿、研修会での研究発表など、レポート作成と共通するスキルが求められます。様々な研鑽の場で得た知識や実体験からの気付き等を、ご自身の言葉でまとめていく作業を通じて、指導力向上につなげていきましょう。
課題レポート執筆のポイント
課題レポートにはタイトルをつけましょう。
タイトルがあると、何について論じている文章なのかということが明確になり、読み手が興味を持ちやすくなります。
タイトルに見合った内容になるよう、論理立てて文章構成を考えましょう。
まず冒頭に御自身の見解や問題意識を簡潔に述べると、以降の展開につなげやすくなります。そこに加えて知識やレッスンでの経験、セミナーで学んだ内容の応用例等を盛り込むと、文章に説得力をもたせることができます。文章を通して一貫した「主張」があるか、その内容がタイトルと食い違っていないかを、提出前に見直してください。
◆ ご自身が足を運んだセミナーの内容を題材として執筆する場合
セミナーレポートと同水準の内容になっていませんか?
セミナーレポートでは、講座内容のメモ書きや感想、講師の先生へのメッセージ等をご記入いただくことが多いかと思います。課題レポートにおいては、講座内容を御自身で咀嚼した上で、導き出された独自の見解を述べていただきたいと考えています。セミナー内容をそのまままとめるのではなく、そこから芽生えた問題意識や、指導への展望を述べてください。
尊敬する先生がいるあまり・・・偏った内容になっていませんか?
尊敬する先生、目標にしたい先生がいらっしゃることは素晴らしいことです。しかし、指導者ライセンス取得を目指す先生方には、より広い視野をもってピアノ指導と向き合っていただきたいと考えています。そのためにも、いろいろな先生のセミナーに足を運ばれることをおすすめします。同じテーマの講座でも、講師の先生がかわると様々な角度から知識を得ることができます。課題レポートとあわせてご提出いただくセミナーレポートは、2人以上の先生のセミナーレポートをご提出されることを推奨いたします。
◆ 日頃のレッスン内容に基づいた内容で執筆する場合
「自分語り」が多すぎる文章になっていませんか?
現在の指導法を確立させるまで、先生方はそれぞれ悩み、学び、紆余曲折を経てこられたことと思います。しかし審査員は、先生方御自身の背景よりも、今実践している指導法の意義や効果、発想力をみたいと考えています。是非日頃のレッスンを客観的に観察し、自己評価をする癖をつけてみてください。試験の名称でもある「エッセイ」は「随筆」と訳されることも多いですが、ここではあくまで「小論文」としての体裁を保った文章になるよう、心がけてみてください。
課題レポート例
導入期生徒の指導に際しての留意点
何事においても最初が肝心で、導入期のピアノ指導こそ一番大切であると考えています。主に小さな子供が相手である導入指導はとりわけ教師の創意・工夫が大きく必要とされるものでしょう。そのために教師は方向性をしっかり持った上で様々な指導法について常に勉強して引き出しを多く持っていなければならないと思います。一人一人の子供の個性をじっくり見極め、その子に合った指導法を見つけていき、決して音楽嫌いにさせてはいけないのです。
導入期の指導でぶつかる最大の問題に読譜がありますが、これは現代の小さな子供にいきなり五線から始めてしまうことに無理があるからだと思います。目よりまず耳から音を入れていくのが良いのではないかと私は考えています。たくさんの音・音楽を聴いて自分も音を出してみたいという気持ちになったところでピアノに触ってみるのがベストだと思うのです。これは耳の発達が手先の発達より早く6歳くらいでピークに達すると言われていることからも有効な方法であると言えます。耳は、将来、ペダルを使用する時や、自分の音を聴いて音色を作っていく時に非常に大事になってきます。よってまず聴いて、そして歌ってみる、それから弾く、というプロセスを踏んでいくのがスムーズだと考えています。ただ耳にあまり偏ると楽譜を見なくなってしまい、読譜の力がつかなくなってしまうので、うまくピアノに興味を持ったら、音符を教えていきます。この時に気をつけるのは、楽しく音符を覚えてもらうことです。今は様々はカード等の教材が入手できるのでそれらをうまくとりいれ遊び感覚で進めるようにします。そうして音符と鍵盤の位置がわかってきたところですが、音符を並べただけでは音楽になりませんから、同時にリズム感も身につけていかなければなりません。音楽の三要素である、リズム、メロディー、ハーモニー、これらをこの順番通りに、バランス良く、大切な導入期に教えていくことが、将来のための基礎となっていくのです。このように導入期のピアノ指導においてはソルフェージュが欠かせないものであると言えます。
ピアノ奏法の観点から導入期の指導で大切なのは、手の形と脱力であると思います。これらは小さな子供には早い、ということはなく、むしろ小さいうちにこそ身につけておくべきことだと思っています。すぐにできるようになることではないので、長い目で見て、しかし妥協することなく、根気強く導いていけばいつか必ず出来るようになります。
以上導入期の指導について述べてきましたが、どんな子供にも秘めた可能性があり、それを引き出して導いてやるのが私達ピアノ教師の役目であると思っています。たとえ音楽の道へ進まなくともその子なりに音楽を楽しみ、人生の傍らに音楽がある、そうした人が増えて音楽愛好者の底辺が広がっていくことは私達皆の願いではないでしょうか。そのための基礎作りをあせらず、休まず、あきらめずにやっていきたいと思います。
コメント
- 3名の審査員による採点を行っております。
- 導入期において大切なことを、論理的にわかりやすく述べられています。(審査員A)
- 意識の高さや視点の広さがうかがえ、また簡潔な文章で大変良いです。(審査員B)
作曲家・歴史的背景の理解と演奏指導
ピアノを弾いていく上で、レベルが上がるにつれて曲の内容も濃くなり、作曲家の時代や、国によっても奏法が異なり、芸術性の高い演奏が求められるということを、自分でも感じ、これまで沢山のベテラン先生方の講座で学び、新しい発見の連続でしたので、それを生かせるレッスンをしていきたいと思い、ここで述べたいと思います。
特に印象の強かった、赤松林太郎先生のバロックについての講座で学んだことを中心に書かせていただきたいと思います。
バロック音楽は、その前の時代のルネッサンスから受け継がれ、舞曲(フランスで生まれた)、対位法、ファンタジア、この3つが柱になるということです。
ルイ14世の時代には、メヌエット、クーラント、(フランス風)、ジーグが流行り、その中でクーラントは王が最初に踊るものと言われ、王にしかできないステップだったそうです。メヌエットは2種類あり、最初に左手が和音で始まる、テンポが落ち着いて、装飾も多く入った優雅なものと、最初に和音のない6拍で1フレーズの軽やかなテンポのものがあるということも、発見でした。前述の方は、踊るためのメヌエット、後述の方は器楽的なメヌエットということも学びました。
同じく、ガボット(フランス)も踊るためのものと、器楽曲としてのテンポの速いガボットがあるということです。
これまで、メヌエットやガボットというと、当然踊りの曲だと思い込んでいたのですが、大きな誤解でした。知らないということは、恐ろしいと思います。その曲の特徴を知った上で演奏をしなければ、全く違う音楽になってしまいます。
ルネッサンスの音楽があってバロックが始まったわけですが、バッハについて書きますと、バッハはイタリア、フランス両方の様式をもってきて、作曲されたそうです。よく聞かれるクーラントはフランス様式で、テンポは遅い、コレンテはイタリア様式でテンポは速いということ。
インベンションの中でも、3番はDdurでフランス風で優雅、4番はdmollでイタリア風ということもお話いただき、今まで考えたこともありませんでした。ですので、数多くあるバッハの作品は、フランス風なのか、イタリア風なのかと、疑問を持ちながら、取り組むべきだと思いますし、生徒にも意識させるとよいと思います。
そしてバッハの作品は、2声の曲でも3声の曲でも、4声(ソプラノ、アルト、テノール、バス)でできていると考え、それぞれのパートの音色を考えて演奏につなげると、立体的な演奏になるということを伺い、これからのインヴェンションの指導の仕方も広がり、生徒と一緒に音楽を作っていくことが楽しみになりました。
ひとりの作曲家だけでも音楽の背景には沢山のことがあり、それが文学、絵画、建造物など音楽と深い関係があるわけですので、奥の深さを改めて感じました。
今まではなんとなくバロックの曲はこんな感じ・・・・というような漠然としたものしかなく、大変お恥ずかしいことでした。ついつい目の前にある、楽譜を必死に見て、それをピアノで弾く作業になりがちですが、それでは音楽の質は高まりません。
常にアンテナを張り、その時代の背景との結びつき、関わりを考えて演奏すべきだと強く感じました。指導者の知識が豊富であれば、生徒にも伝えられる引き出しが増えますし、生徒本人も指導者の影響をうけて、自発的に調べるようになり、作曲家の意図する演奏に近づけるのではないかと思います。
コメント
- 3名の審査員による採点を行っております。
- バロック作品の歴史的背景の理解と演奏指導について、短い文章の中でよくまとめておられます。(審査員A)
- 問題意識がセミナー受講から具体的に絞られ、発見から指導の展望へと簡潔にまとめられています。(審査員B)
【広告】