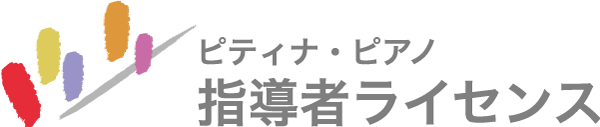「イメージ」は音楽を喪失させる?~音楽とことばのかかわり(2)~(執筆:石川裕貴)

執筆:石川裕貴
皆さんは、音楽を演奏するとき、もしくは音楽を聴くとき、何を考え、何を感じますか。音楽の構造や形式、作曲家の背景、音楽から連想される「イメージ」や「感情」等、様々な要素を思い起こすことと思います。
音楽において、「イメージ」や「感情」が重視されるようになったのは、18世紀頃のことです。バッハの受難曲では、キリストの苦悩や悲しみが音楽として表現されています。それは、キリストもまた「我々と同じように感じ、考える」という人間観なしには成し得なかったものでしょう。そういった感性がロマン派音楽で更に拡張され、一義的に「音楽とは感情にかかわるものである」という信念が普遍的原理となり、ジャーナリズムにおいてのみならず、音楽心理学等の学問や音楽療法の形成にまでかかわっています(若尾 2017)。
このことは、学校での音楽教育においても同様であり、「心の中に思い描く全体的な印象」や「喚起された自己のイメージや感情」を音楽活動の拠り所としています(文部科学省 2018)。また、ピアノ教育においても、筆者は「ここは天使が囁くように」「ここは悲しい感じで」等、「イメージ」や「感情」に偏ったレッスンを受けていました。しかし、このようなことばの扱い方は、鳴り響く音楽そのものではなく、音楽から派生した「イメージ」や「感情」に価値を置くこととなります。果たして、そのようなことばの行く先に、鳴り響く音楽は存在し得るでしょうか。
今回は、音楽教育に求められることばの在り方について、音楽とことばのかかわりを切り口として、哲学的に検討していきたいと思います。
芸術における解釈が歴史的に初めて現われたのは、科学的啓蒙が波及し始めた古典時代の末期だと言われています。この「古典的解釈」について、ソンタグ(1996、pp.19-20)は以下のように述べます。
啓蒙思想がもたらした現実主義的な考え方によって、それまでもっていた神話的な力とその信憑性は崩壊していくこととなりました。当時、神話や聖書等を信仰してきた人たちにとっては、アイデンティティをも崩壊させる危機に面してしまったというわけです。そこで、神話的な力とその信憑性を取り戻すために、神話を現実に重ね合わせようと、字義通りの意味の上にかぶせて、もう一つの意味を打ち立てようと試みたというわけです。その結果、「古典的解釈」が生じたのでした。
 図 1 「古典的解釈」の縮図
図 1 「古典的解釈」の縮図その後、解釈がさらに発展していくこととなるのですが、所謂「今日の解釈」は、「古典的解釈」と比べてさらに複雑化することとなりました。「古典的解釈」が、あくまでも現実と神話との乖離を埋めるための方便であったのに対し、「今日の解釈」は、解釈に人文科学的、学術的な普遍を付与する試み、すなわち「真の意味」の追求を目的とする行為となったのでした。
例えば、マルクス主義批評においては、「いかに複雑で間接的な仕方でであれ、どの時代の社会的、生産的諸関係を反映しているものとする考え方」(ハイマン 1974、p.12)が、フロイト主義批評においては、「夢との類推にもとづいて、抑圧された願望の擬装した表現及び充足……そして、その根底にあるものとして、意識下の精神的次元や表現原理と検閲原理との間のある衡突という」(ハイマン 1974、p.12)考え方が芸術の根源として捉えられます。このような解釈について、ソンタグ(1996、pp.21-22)は以下のように続けます。
つまり、マルクスやフロイトの見解では、芸術から掘り起こされた解釈による「真の意味」がなくては、芸術を理解することはできない、ということになります。
 図 2 「今日の解釈」の縮図
図 2 「今日の解釈」の縮図このことについて、ソンタグ(1996、pp.22-23)は、以下のように批判します。
例えば、音楽学者のフレーリヒは、ベートーヴェン作曲《交響曲第9番》の第1楽章を、音楽におけるある種の自己肖像画だと見なしました。第1楽章では、絶えず変化する対比的な響きの連鎖を、難聴による苦悩やベートーヴェンの矛盾した感情を表現したものだと解釈しました。そして交響曲全体を通じて、難聴による心理的打撃に対するベートーヴェンの奮闘を描き、最終楽章では、シラーの「歓喜の歌」に曲をつけ、苦悩を超えたベートーヴェンの勝利を表現したと解釈しました。つまり、フレーリヒは、《交響曲第9番》から掘り起こされた「真の意味」から、その作品の根源や心理を追求しようとしたのでした(Cook 2000)。
しかし、鳴り響く《交響曲第9番》からベートーヴェンの苦悩や勝利を指し示すことなどあり得ないですし、何を考え、何を感じてベートーヴェンがこの楽曲を作曲したのか、そして演奏されたのかなど、当の本人しか分かり得るはずがありません。
ソンタグ(1996)は、このような「今日の解釈」によって、芸術に対する我々の感受性を毒させると同時に、芸術そのものを貧困化させていると警鐘を鳴らします。芸術の〈形式〉と共に、感覚的経験の鋭敏さをも喪失させていることに、我々は何の違和感も持たなくなってしまっているのです。
では、芸術そのものや我々の感覚的経験を喪失させないことばの在り方とは、一体どのようなものなのでしょうか。ソンタグ(1996、p.32)は、「透明」という用語を用いて、以下のように述べます。
また、ソンタグ(1996、pp.32-33)は以下のようにも述べます。
以上のことをまとめると、「この作品には、実は作者のこのような意図が込められている」「Aがこう表現するのは、Bという文脈(歌詞、社会背景等)によるのだ」等、芸術作品から派生した「イメージ」や「感情」等の〈内容〉による「ことばの置き換え行為」が、芸術そのものの根源とはなりません。むしろ、それは個人の身勝手な解釈の押し付けにすぎず、そこに芸術そのものなど存在し得ないのです。このような事態を避けるためには、芸術の〈形式〉に着目し、その艶や肌理を「透明」に写し取る語彙、つまり〈反解釈〉するためのことばを追求することが重要となるのです。
 図 3 艶や肌理を「透明」に写し取る語彙
図 3 艶や肌理を「透明」に写し取る語彙このことを音楽教育に援用すると、「音」のコミュニケーションを充実させ、「どのような音色を奏でるのか」「強弱の変化をどのように付けるのか」「リズムや速度はどのように変化させるのか」について、「透明」に追求する語彙や用語が重要ということになります。それによって、演奏者や鑑賞者が「音」そのものに耳を傾け、「透明」に音楽表現を創意工夫したり、音楽を批評したりすることができるようになるのです。
さて、ここまで御託を並べてきましたが、これまでにピアノ教育において、ピアノ受講者にどのような指導をしてきたのか、もしくはピアノ教師からどのような指導を受けてきたのか、思い起こしてみてください。「イメージ」や「感情」といったことばによる二次的生産物によって、鳴り響く音楽が矮小化されていないでしょうか。
読者の皆様には、まずは耳を研ぎ澄まし、徐々に喪失しつつある(であろう)感覚的経験の鋭敏さを取り戻すことで、あの忘れていた感覚を呼び覚まし、さらなる音楽の奥深さを追求していってほしいと切に願っております。
- Cook、 N. (2000) Music: A Very Short Introduction. ed. Oxford University Press.
- 今田匡彦(2015)『哲学音楽論:音楽教育とサウンドスケープ』恒星社厚生閣.
- グレーブス、R.(1998)『ギリシア神話』高杉一郎訳、紀伊國屋書店.
- シェーファー、R. M.(2006)『世界の調律:サウンドスケープとはなにか』鳥越けい子他訳、平凡社.
- ソンタグ、S.(1996)『反解釈』高橋康也、出淵博他訳、筑摩書房.
- ハイマン、S. E.(1974)『批評の方法1:現代文学批評』富原芳彰、川口喬一訳、大修館書店.
- プラトン(1967)『パイドロス』藤沢令夫訳、岩波書店.
- 文部科学省(2018)『中学校学習指導要領(平成29年度告示)解説音楽編』教育芸術社.
- 若尾裕(2017)『サスティナブル・ミュージック:これからの持続可能な音楽のあり方』アステルパブリッシング.