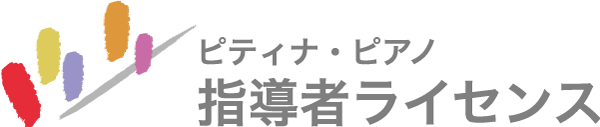「ピアノは歌う」―19世紀のパリ国立音楽院ピアノ教授たちが語る演奏表現の要点(1)(執筆:上田泰史)

執筆:上田泰史
人間の声が奏でる歌の魅力を楽器で表現したいという思いは、今も昔も変わりません。その背後には、歌の魅力を追体験したいというだけではなく、楽器で歌をいかに表現できるかという創意も働いているに違いありません。人間の声を伴わない器楽というジャンルが、それだけで作曲家や演奏家の思考や精神を表現し、聴き手の想像力に訴える力があるとする考え方は、18世紀の後半から19世紀初めにかけて現れてきました。その背景には、言葉を必要としない楽器の「声」こそが果てしない精神世界を表現すると考える、音楽におけるロマン主義の思潮があります。この章では、音楽におけるロマン主義の浸透とともにピアノが声楽的な表現を希求するようになった過程の一側面を、教育という視点から見ていきます。
ピアノ指導において、生徒に伝えたい内容を100パーセント言語化することは不可能です。歌唱表現を実践するために鍵盤上で指や手がどのように動作するのか。手首、腕、方、背中、腰が手とどのように協働するのか。個々の場合に応じた身体の動きはきわめて複雑です。ショパンをはじめとした優れたピアノ教師たちは、その技法をそれぞれの仕方で生徒に実際に聴かせ、見せながら教授してきたのです。「ピアノで歌う技法」は、明示的には言語化し難い、身体化された知に属しています。
ドイツの批評家エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマン(1776~1822)は、『カロ風幻想作品集』(1814年刊)所収の「クライスレリアーナ」と題する評論集で、ベートーヴェンの器楽に触れ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの交響曲に「ロマン的」な特質を認めました。(ここで言う「ロマン的」とは、本来はラテン語から派生したロマンス諸語で書かれた中世の空想・幻想文学の精神に根ざした、という意味に捉えてください。)ホフマンにとって、とくにベートーヴェンの器楽は、言葉では言い表すことのできないものを表現するからこそ、この世ならざる世界への扉を開いてくれるジャンルでした。こうした新たな思潮を起点として器楽の美学的位置づけは大きく変化し、ドイツでもフランスでも、言葉の助けを借りずにそれ自体で力強い表現力をもつ音楽ジャンルとして認められるようになりました。
器楽が「いわく言い難いもの」を表出するという新しい考え方は、ピアノ教育の方法論とは必ずしも一致しません。それどころか、矛盾しているようにすら思えます。というのも、方法論(メソッド)とは、言葉でしか体系化できないものだからです。実際、パリ国立音楽院草創期(18世紀末)以降、教授たちによって書かれた数々のピアノ・メソッドを読んでみると、精神の「無限の王国」といった現実離れしたホフマン流の比喩表現に出くわすことはありません※1。しかし、かといって、ピアノ教則本は運指や種々の演奏技法の羅列や説明ばかりに終始していたわけでもありません。器楽が声楽に劣らず表出的であると考えられるようになるにつれ、ピアノ教育は、ピアノがいかに声楽やオーケストラの表現力を手中に収められるか、という野心的な目標を掲げるようになります。ピアノは、言葉の助けを借りずに、いかにして聴き手に語りかけることができるようになったのでしょうか。
若いピアニストが[ピアノで]歌う技法に磨きをかけたいと思うなら、イタリア楽派の大歌手を手本とすべきでしょう。

『完全ピアノ教程』の著者エレーヌ・ド・モンジュルー(1764~1836)は貴族出身のピアニスト兼作曲家で、1795年にパリ国立音楽院が設置された当初、約2年間、ピアノの教授を勤めました。1810年代に執筆され、1820年頃に刊行した3部からなるピアノ教則本が、この『完全ピアノ教程』です。豊富な実例と124曲の自作練習曲・フーガ・カノン・幻想曲を収めたこの教本の序文で、モンジュルーはピアノ演奏表現の原則を掲げています。それは、ピアノ学習者はイタリアのオペラ歌手の技法を手本にすべし、というものでした。ピアノは打鍵の強さに応じて強弱をつけることができるので、まるで歌の抑揚やレガートを聴いているかのように錯覚させることができる――それこそがピアノ演奏技法の要点だと、モンジュルーは第1部の序文で主張しています。 実は、モンジュルーの前にも後にも、ピアノ教師たちは繰り返し同じことを主張してきました。彼女と同じく初期のパリ音楽院で教鞭をとったジャン=ルイ・アダン(1758~1848)は、1804年に出版したパリ音楽院公式ピアノ教本でこう書いています※2。
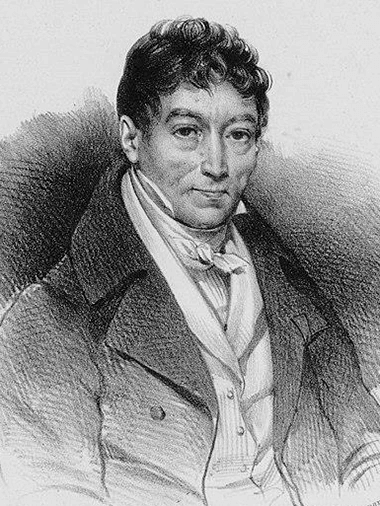
この教えは、アダンの弟子のフレデリック・カルクブレンナーにも受け継がれました。1831年に刊行されたカルクブレンナーのピアノ教本『手導器を用いてピアノ・フォルテを学ぶためのメソッド』には、次のような記述があります※3。

ピアノの演奏表現において、なぜオペラ歌手、それもイタリアの歌手たちの歌唱がピアニストの範として異口同音に推奨されたのでしょうか。一つの理由は、クラヴサン(チェンバロ)に対して主張された、ピアノという楽器の特性にあります。1774年に啓蒙思想家ヴォルテールによって「クラヴサンと比べれば鍋釜製造者の楽器にすぎない」※4と評されたピアノは、その17年後の1791年、音楽理論家ジェローム=ジョゼフ・ド・モミニから正反対の積極的な評価を受けます※5。

クラヴサンに対してピアノを表出的な楽器として捉える立場は、その13年後に出版されたジャン=ルイ・アダン教授のパリ音楽院公式ピアノ教本にも見て取ることができます※6。

冒頭に掲げたモンジュルーの言葉は、こうしたピアノの「再現力」に力点を置く世紀転換期のピアノ演奏美学に根差していたのです。しかし、モンジュルーはピアノが完全な再現力をもつ楽器だとは考えていませんでした。彼女に言わせれば、ピアノは打鍵後に音が減衰するので、「音の一つ一つを長く伸ばすという[声の]特性を模倣すること」ができません。
しかし、この欠陥を補うための創意工夫こそが、ピアノ演奏法の鍵になるのだ、と主張します※7。
声楽を模倣するということは、単に真似をするということではなく、聴く者の耳に錯覚を生じさせる実践的かつ創造的なプロセスであったということがわかります。これは、現代でも通用する教えです。
音楽は演説と同様に、語、文(フレーズ)、節(ペリオード)で出来ており、いずれの場合も、休止点が決められています。弁論家の言葉と同様に、ピアニストの言葉もまた、息継ぎで分断されてはなりません。ピアノによるフレージングの技法、それこそが、歌手にとっての息継ぎの技法なのです。

音楽を文法や弁論術(雄弁術)との比較によって説明することは、古くから盛んに行われてきました。ドイツ語圏ではヨハン・マッテゾンやヨハン・クリストフ・コッホ、レオポルト・モーツァルト、フランスではミシェル・ド・サン=ランベール、アレクサンドル・ショロン、アントワーヌ・レイシャ(レイハ)など多くの教育者・理論家が、言語の比喩を用いて作曲形式や演奏様式の原理を説明してきました※8。上に引用したヅィメルマンの言葉も、アカデミックな教育を受けたピアニスト兼作曲家たちが共有していた、伝統的な音楽修辞学の知識に根ざしています。
「フレーズ」という言葉はもともと文法用語で、「文」を意味します。つまり、フレージングとは、文法的な区切りを意識して演説や朗読の内容が説得力をもって聴き手に伝わるように発話する、ということです。ヅィメルマンの教本の約20年前に出版されたモンジュルーの『完全ピアノ教程』でも、フレージングの重要性が強調されています。モンジュルーによれば、イタリア楽派の歌手の美点は、フレージングの技法にあるといいます※9。
上手にフレージングをするということは、音楽の文法を理解し、楽曲の構造や奏者の意思を明晰に聴き手に伝えることに他なりません。しかし、ヅィメルマン教授が書いているように「正確なだけの演奏は、何も言っていないのと同じ」※10です。旋律の演奏は決して機械的に行われるべきではなく、規則的な伴奏に対する柔軟な動きがなければ、説得力を持たないというわけです。演者である歌手の歌には感情が乗らなければならないので、表現に応じて旋律のテンポには伸縮が生じます(いわゆるアゴーギグ)。和声や旋律の理論的な区切れを理解したうえで豊かな表情を付ける、説得力ある語りのような表現こそ、劇的なピアノ演奏表現の理想だったのです。
歌唱パートを担う右手は、おそらく歌手と、そして左手は歌手を伴奏するオーケストラと比較することができるでしょう。
当時の演奏表現論が立脚していた弁論術は、古代ギリシャのアリストテレスや古代ローマのキケローから脈々と受け継がれてきました。修辞学(レトリック)を基礎とする弁論術の伝統は、20世紀に至るまでピアニストたちの間で生きていました。例えば、20世紀の名ピアニスト、アルド・チッコリーニは、次のように書いています※11。
音楽は演説ですので、音楽でも同じことが言えます。それは、他の声部を落として、ひとつの単語上のある音節にアクセントを置き、感情を表現する言葉です。
「テンポ・ルバート」についてチッコリーニ氏が語ったこの文章は、モンジュルーが1810年代に語ったこととほとんど同じことを言っています。こんにち、ピアノ音楽における「ルバート」は「少しテンポを緩めること」ぐらいに理解されていますが、じつは、規則的な拍節の中でテンポを柔軟に伸縮させ、表情豊かな声のように演奏する、という意味を持っていました。テンポ・ルバートとは、直訳すれば「盗まれた時間」という意味です。「時間を盗む」とは、規則的な伴奏のリズムに対して、旋律のタイミングを先取りしたり、遅らせたりすることに他なりません。
1862年にパリ音楽院教授の座についたショパンの弟子ジョルジュ・マチアスは、テンポ・ルバートを説明するときに、やはり弁論家を引き合いに出しています※12。

ピアノの大譜表で表現された歌唱的な楽曲――例えばショパンのノクターン――は、一見、旋律と伴奏パートを別々の奏者が演奏しているようには見えないので、右手と左手のタイミングが同期しがちです。しかし、19世紀の前半から、ピアノ教師たちは歌唱的な様式のピアノ曲については、旋律と伴奏を別個のパートとして表現することを強調してきました。モンジュルーがイタリア楽派の歌手の美点として指摘したのは、一貫したテンポで奏でられる伴奏と、その上で自由に展開される旋律です。フレーズの途中で、歌は伴奏に対して少し遅れをとったり、拍を先取りしたりしますが、最終的には終止形で帳尻を合わせます。この伴奏の規則的な流れと声楽の伸縮自在の流れをピアノ上で表現することこそ、劇場歌唱様式をピアノ一台で再現するということだったのです※13。
この原則は、1840年にパリ音楽院教授ジョゼフ・ヅィメルマンが出版した新しいパリ音楽院用のメソッド『ピアニスト兼作曲家の百科事典』でも簡潔に指摘されています。「バスのテンポは、旋律の性格に応じて必要とされる闊達さや気まぐれな動きの影響を受けてはいけません。」※14この旋律と伴奏の関係は、レオポルト・モーツァルトの『ヴァイオリン奏法』(1787年刊)でも言及された、古くからある演奏様式の原則でした※15。教師としてのショパンもまた、弟子たちに同様のことを語っていたことが知られています※16。20世紀も後半になると、右手と左手のずれは避けられるようになり、両手が同じタイミングでテンポを緩める様式が一般的になりました。それは、声楽(オペラ文化)と器楽が分離してしまったことに起因する、文化的な帰結なのかもしれません。
しかし今日、チェンバロ・フォルテピアノ奏者、さらにはモダン・ピアノ奏者の中にも、このズレを採用する若手音楽家が見られるようになりました。この「ズレ」がどのような意図のもとに用いられているのか、現代の聴き手がどのように捉えているのか、「ルバート・リバイバル」への興味は尽きません。
- ただし、練習曲というジャンルでは、実用的な目的を超えてロマン主義への接近が見られました。イグナーツ・モシェレスは《24の練習曲》作品70の序文でホフマンの言葉(「器楽はあらゆる芸術のなかでもっともロマン的である。なぜなら無限なるものだけが、その主題だからである」)を引用しています。練習曲とロマン主義については、拙著『「チェルニー30番」の秘密――練習曲は進化する』第2章を参照してください。
- Jean-Louis Adam, Méthode de piano du Conservatoire, adoptée pour servir à l’enseignement dans cet établissement, Paris, Imprimerie du Conservatoire de Musique, 1804, p.149.
- Frédéric Kalkbrenner, Méthode pour apprendre le piano-forte à l’aide du guide-mains op. 108, Paris, I. Pleyel et Cie, 1831, p.9. 引用中で言及されているフランスのテノールのピエール・ジャン・ガラとカストラートのジローラモ・クレッシェンティーニは、どちらもパリ音楽院教授を務めたことがあります。後者は名誉教授教授でした。
- 1774年12月8日付のデュ・ドゥファン侯爵夫人(la marquise Mme du Deffand)への手紙に見られる表現。
- Jérôme-Joseph de Momigny, « Piano. (Piano-forté ou forté-piano), Encyclopédie méthodique. Musique, vol.2, Paris, chez Panckoucke, 1791, p.267.
- Jean-Louis Adam, Méthode de piano du Conservatoire..., p.I.
- Hélène de Montgeroult, Cours complet pour l'enseignement du forté-piano conduisant progressivement des premiers éléments aux plus grandes difficultés, partie 1, Paris, Paricier, [ca 1820], p.I.
- 詳しくは次の文献を参照のこと。マーク・エヴァン・ボンズ『ソナタ形式の修辞学――古典派の音楽形式論』、土田英三郎訳、東京:音楽之友社、2018年。
- Hélène de Montgeroult, Cours complet pour l'enseignement du forté-piano conduisant progressivement des premiers éléments aux plus grandes difficultés..., p.1.
- Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman, Encyclopédie du pianiste compositeur, 2e partie, Paris, chez l’auteur; Troupenas, 1840, p.58
- パスカル・ル・コール『アルド・チッコリーニ 我が人生ピアノ演奏の秘密』、海老彰子訳、東京:全音楽譜出版社、2008年、 92-93頁.
- Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin vu par ses élèves, Paris, Fayard, 2006, p. 74.
- 実際に、どのように右手と左手のタイミングをずらしていたのかについては、C. サン=サーンスによるショパン《ノクターン》作品15-2を分析した筆者の下記のケース・スタディを参照のこと。Yasushi Ueda, “Tempo rubato as Rhetorical Means: An Analysis of the Performance of Chopin’s Nocturne op. 15-2 by Camille Saint-Saëns (1905)”, Journal of the Serbian Society for Music Theory, 1(1), March 2022, p.34-54.
- Joseph Zimmerman, Encyclopédie du pianiste compositeur..., 2e partie, p. 59.
- Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg, Johann Jacob Lotter, 1756, p. 263.
- ショパンにピアノを師事したヴィルヘルム・フォン・レンツはこのように語っています。「ショパンの演奏の特徴は、彼のルバートにあった。リズムは全体として常に保たれる。私は彼[ショパン]がこのように言うのをしばしば聞いた。『左手は聖歌隊の指揮者で、遅れたりゆがめられたりしてはいけない。それは柱時計です。右手で、あなたがしたいこと、できることを弾きなさい。』」(Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin vu par ses élèves..., p. 74.)